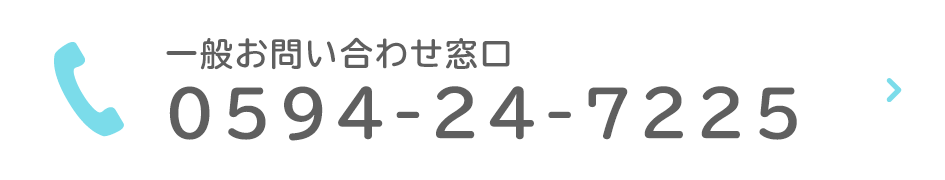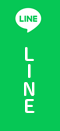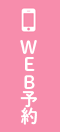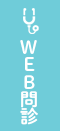気管支喘息(小児喘息)とは
気管支喘息は、さまざまな原因で空気の通り道である気道(気管支)が敏感になり、その結果、気管支の壁に炎症を起こし、気管支の壁が分厚くなり、空気の通り道が狭くなり「ヒューヒュー・ゼロゼロ」を繰り返す病態のことを指します。特に、乳児の場合は、風邪をひくとよく喘鳴を繰り返し(喘息様気管支炎)、そばに居て明らかな喘鳴を3回以上繰り返す場合は「乳児喘息」と定義されます。年齢とともにいつのまにかゼロゼロしなくなる一過性(一過性初期喘鳴群)のことが多いですが、幼児期以降も繰り返すものに、非アトピー型喘鳴群、IgE関連喘鳴/喘息群があります。喘鳴を繰り返すことで、気管支が傷つき、傷ついた気管支はより敏感になり、炎症と修復を繰り返す(慢性の気道の炎症)ことにより気管支そのものがリモデリングといって鉛のように固くなってしまうと、大人の喘息、ひいてはCOPD(慢性閉塞性肺疾患)に移行していくこともあります。
気管支喘息の原因
気管支喘息の原因は一つではなく、いくつかの要因が組み合わさって発症すると考えられています。
アレルギーが関係するもの
ダニやハウスダスト、花粉、ペットのフケ、カビなどのアレルギー物質が原因となります。これらのアレルギー物質を吸い込むと、体の中でアレルギー反応が起こり、気道の炎症が引き起こされます。
アレルギーが関係しないもの
・風邪などのウイルス感染症: 風邪をひくと、気道が刺激され、喘鳴が誘発されることがあります。代表的なウイルス疾患として、RSウイルス、ヒトメタニュウーモウイルス、パラインフルエンザウイルスなどがありますが、一般的な風邪ウイルスであるライノウイルスでもゼロゼロすることはよくあります。RSウイルスに罹患すると、気管支が傷つき、よくゼロゼロを繰り返すことがよくあります。
・運動や気候の変化: 激しい運動をすることで喘息発作が起こる場合があります(運動誘発喘息)。また、寒暖差(朝方に咳き込む)や気圧の変化(低気圧、台風など)によりゼロゼロすることもよくあります。
・たばこの煙: 受動喫煙も喘息発作のリスクを高めます。子どもの前でのタバコは絶対に止めましょう。他に心身のストレスや疲労が喘息発作を誘発することもあります。
喘息発作強度の判定基準
小発作:喘鳴は軽度、陥没呼吸、呼気延長はなく、横になることができ、急いで歩くと苦しいが、睡眠は眠れる。SpO2は96%以上
中発作:喘鳴は明らか、陥没呼吸を認め、呼気延長があり、横になることができず、座位となる。呼吸困難は歩行時著明で睡眠は時々目を覚ます、やや興奮状態である。チアノーゼは認めない。SpO2は92%~95%
大発作:喘鳴、陥没呼吸は著明で、呼気延長は明らかで姿勢は前かがみになり、歩行は困難で、横になって睡眠できない。興奮状態でチアノーゼは認めることがある。SpO2は91%
呼吸不全:喘鳴は減少又は消失(喘鳴が聞こえない)、陥没呼吸、呼気延長は著明で、歩行不能で意識は錯乱状態、睡眠できない。チアノーゼを認める。SpO2は90%以下
注意点:大発作以上を認める時は、命の危険もあり、夜間・深夜でも救急対応及び入院が必要になります。
気管支喘息の重症度分類(発作頻度による)
間欠型
・年に数回、季節性に咳嗽、軽度喘鳴が出現する。
・時に呼吸困難を伴うこともあるが、β2刺激薬の屯用で短期間に症状は改善、持続しない。
軽症持続型
・咳嗽、軽度喘鳴が1回/月以上、1回未満/週未満。
・時に呼吸困難を伴うが、持続は短く、日常生活が障害されることは少ない。
中等症持続型
・咳嗽、軽度喘鳴が1回/週以上。毎日は持続しない。
・時に中・大発作となり日常生活や睡眠が障害されることがある。
重症持続型
・咳嗽、軽度喘鳴が毎日持続する。
・週に1~2回、中・大発作となり日常生活や睡眠が障害される。
最重症持続型
・重症持続型に相当する治療を行っていても症状が持続する。
・しばしば夜間の中・大発作で時間外受診し、入退院を繰り返して、日常生活が制限される。
急性発作への治療
発作強度によりますが、小発作では、β2刺激薬の吸入と内服治療を行います。中発作では、β2刺激薬をネブライザーで吸入させ、20~30分間隔で3回まで反復することができます。外来にて、吸入器を貸し出し、自宅での吸入療法及び、β2刺激薬の内服、及び短期的にステロイド内服を行い、経過をみることもありますが、吸入を繰り返してもSpO2の改善がみられない場合は、入院の適応を考慮します。大発作、呼吸不全は夜間・深夜でも緊急入院の適応になります。発作時は、脱水による喀痰を詰まらせ窒息し、死亡することもあります。水分をなるべくたくさん取り、痰を出しやすくします。
小児気管支喘息の長期管理と治療目標
喘息は、基本病態として気道炎症が慢性的に存在し、種々の刺激因子の関与により、気道過敏性の亢進や気道リモデリングを来し重症化・難治化すると考えられています。従って治療は炎症抑制を目的に喘息憎悪因子の軽減を図るための環境整備と薬物療法を組み合わせた長期的な包括的介入を行います。
小児気管支喘息の日常治療の目標は、
症状のコントロール
・ β2刺激薬の屯用が減少、又は必要がない。
・ 昼夜を通じて症状がない。
呼吸機能の正常化
・ ピークフローやスパイログラフが正常で安定している。
・ 気道過敏性が改善し、運動や冷気などによる症状誘発がない。
QOLの改善
・ スポーツも含め、日常生活を普通に行うことができる。
・ 治療に伴う副作用が見られない。
気管支喘息の治療の目標は、発作が起きないように気道の炎症を抑え、日常生活を健やかに送れるようにすることです。適切な治療と管理で症状をコントロールすることができます。
主な治療薬は以下の2種類です。
1)発作治療薬(リリーバー)
喘息発作が起きたときに、狭くなった気管支を広げ、息苦しさを和らげるお薬です。短時間作用型β2刺激薬(SABA)には、吸入薬としてサルブタモール(ベネトリン)とプロカテロール(メプチン)があります。経口薬では、ツロブテロール(ホクナリン)や、プロカテロール(メプチン)があります。
2)長期管理薬(コントローラー)
気道の炎症を抑え、発作が起こりにくくするお薬です。毎日継続して使用することで効果を発揮します。ロイコトルエン受容体拮抗薬(プランカスト、モンテルカスト)と吸入ステロイド(フルタイド・キュバール・オルベスコ等)があります。また、吸入ステロイドに長時間作用型β2刺激薬(LABA)であるサルメテロールを加えたアドエア・フルティフォームがあります。基本となる薬であり、症状がなくても医師の指示通りに続けることが大切です。
気管支喘息は、喘鳴を繰り返すごとに気管支の内壁が傷つき、傷ついた気管支はより過敏になり、炎症と修復を繰り返すことで、気管支そのものがリモデリングといって鉛のように固くなってしまうと、大人の喘息に移行していくことがあります。この傷ついた気管支の内壁をスムーズにし、発作を予防していくのが、コントロール薬で、発作のない状態をゼロレベルといい、このゼロレベルをできるだけ長く続けることが治癒に向かう第一歩となります。当院では、3ヵ月毎に評価を行い治療継続するか漸減するかを確認するようにしています。
※参考 薬の吸入方法|小児ぜん息基礎知識|独立行政法人環境再生保全機構
独立行政法人環境再生保全機構より
ネブライザーの使い方
pMDI+スペーサー
(マスクタイプ)の使い方
pMDI+スペーサー
(マウスピースタイプ)の使い方
DPI ディスカスの使い方
喘息のコントロール状態の評価
● 良好 :軽微な症状も全く認めず、β2刺激薬の使用が全くない。
● 比較的良好:軽微な症状が月に1回以上だが、週に1回未満。明らかな喘息発作は認めず、日常生活の制限はあっても軽微、β2刺激薬の使用は月に1回以上、週に1回未満である。
● 不良 :軽微な症状、β2刺激薬の使用は週に1回以上、明らかな喘息発作、日常生活の制限は月に1回以上ある。
1)小児喘息コントロールテスト(C-ACT)
4~11歳の小児を対象とします。 喘息の状態を点数で評価し、治療方針の検討に役立てるための質問紙です。過去の症状の頻度や発作頻度などの質問に回答し、合計点数によって喘息の状態を「良好」・「比較的良好」・「不良」といった段階で評価します。
2)呼吸機能検査
肺の機能(どれだけ空気を吸って吐けるか、その速さなど)を測定し、喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器疾患の診断、重症度の評価、治療経過の確認、そして健康状態の評価を行います。肺活量や1秒量(最初に吐き出せる空気の量)、1秒率(肺活量に対する1秒量の割合)、末梢気道の閉塞状態を示すV°50・V°25があります。
3)呼気中一酸化窒素濃度(FeNO)測定
吐く息(呼気)のNO(一酸化窒素)を測定する検査です。喘息患者の気道上皮では、炎症性サイトカイン(IL4・IL13)によってNO合成酵素(iNOS)が誘導され、大量のNOが産生されるため、吐いた息に含まれるNO濃度が高くなります。この検査でNO濃度を測定することで、気道の炎症の程度を把握し、喘息の診断補助や治療の目安として活用できます。健常者のFeNOの平均値は15.9ppbですが、小児では20以下が低値、20~35が中等値、35以上が高値となります。当院では25以下を目安としていますが、アレルギー性鼻炎でも高値となることがあり、注意が必要です。
アレルゲン(ダニ・ハウスダスト・ペット・花粉)対策
- 寝具は防ダニ加工のものを使用し、定期的に洗濯・乾燥させましょう。
- 部屋の掃除はこまめに行い、特にカーペットや布製のソファはダニの温床になりやすいので注意が必要です。
- 加湿器の使いすぎはカビの原因になるため、室内の湿度を適切に保ちましょう。(50~60%)。
- ペットのアレルギーがある場合は、飼育を避けるか、接触を最小限に抑える工夫が必要です。
- 花粉の飛散時期は、外出時のマスク着用や帰宅時の衣服の払拭などを心がけましょう。
環境整備
- 家族に喫煙者がいる場合は、お子さんの前では絶対に吸わないようにしましょう。お子さんの前の喫煙は絶対禁忌です。
- 室内の温度や湿度を適切に保ちましょう。急激な温度変化は発作を誘発することがあります。
- 手洗い、うがいを習慣づけ、人混みを避けるなど、風邪をひかないようにしましょう。
日常生活での注意点
- 適度な運動を取り入れましょう。ただし、激しい運動で発作が誘発される場合は、事前に医師に相談し、適切な対処法を確認しておきましょう。
- 十分な睡眠をとり、バランスの取れた食事を心がけるなど、規則正しい生活は免疫力を高め、発作の予防につながります。
- ストレスは喘息発作の引き金になることがあります。お子さんが安心して過ごせる環境を整え、ストレスをためないように配慮しましょう。
- 医師から指示された発作時の対処法を家族全員で共有し、いざという時に落ち着いて対応できるように準備しておきましょう。発作治療薬の使用方法を事前に確認しておくことが大切です。
気管支喘息は、お子さんにとってもご家族にとっても不安な病気ですが、正しい知識と適切な治療、そして日々の生活での工夫によって、発作を減らし、元気に過ごすことができます。何かご心配なことがあれば、いつでも当クリニックにご相談ください。


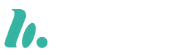
 ホーム
ホーム クリニック案内
クリニック案内 予防接種
予防接種 乳児健診
乳児健診 特殊外来
特殊外来 お母さん
お母さん